基本情報技術者試験の過去問A科目問13について、解説を読んでも理解できない部分があるという質問をよく見かけます。特に、スケジューリング方式の違いや計算の基準について、混乱することがあります。この記事では、スケジューリング方式の理解と、問題での計算方法をわかりやすく解説します。
スケジューリング方式とマルチタスクの関係
まず、スケジューリング方式について考える際に「マルチタスク」という言葉が出てきますが、これは複数のジョブを同時に実行し、CPUの時間を分け合って使う方式を指します。問題文の「待ち行列に並んだ順に実行する」という部分から、マルチタスクの考え方が導かれます。
待ち行列順に実行するということは、ジョブが順番に処理されるという意味ですが、これが必ずしも「到着順」や「ラウンドロビン方式」と同じであるとは限りません。例えば、ラウンドロビン方式では、各ジョブに均等にCPU時間を割り当てるため、実行順序が循環的に変わるのが特徴です。今回の問題では、単に順番に実行するという点に焦点を当てているため、必ずしもラウンドロビン方式とは異なる可能性があります。
5分を基準にした計算方法
解説の表では、最初の15分を3ジョブ×5分で計算していますが、なぜ5分が基準として使用されたのでしょうか?この5分というのは、ジョブAの最初の実行時間(ジョブAのCPU時間)から来ています。
具体的に言うと、問題文の中でジョブAの実行時間が「10分」とされており、この10分を基準にして、他のジョブも処理されていきます。最初に5分ごとの時間配分を行うことで、CPUの時間をどのように分けるかを考える必要があります。
ジョブABCの同時実行時の残り時間の計算方法
ジョブABCを同時に実行した場合、ジョブAが5分で終了した時点で、ジョブBとジョブCの残り時間をどのように考えるかが問題になります。質問者の疑問は、ジョブAが終了した後の残り時間をどのように計算するかという点にありますが、正しい計算方法では、ジョブBとジョブCは、それぞれ残り時間を減らすわけではなく、次の時間帯に処理される順番に影響します。
例えば、ジョブAが5分で終わった場合、残りのジョブBとジョブCは、ジョブAの終了時間後に処理を再開しますが、次の段階でそれぞれのCPU時間を再調整することになります。この段階で、ジョブBとジョブCの残り時間を「5分」と「10分」と考えてしまうのは誤りです。むしろ、最初に予定されたCPU時間に基づいて順番に処理を行う形になります。
スケジューリング方式と計算方法の理解を深める
スケジューリング方式を理解することは、タスクの効率的な実行順序を決定する上で重要です。また、計算方法を正確に理解することで、試験問題の解答にも役立ちます。
基本情報技術者試験では、スケジューリングに関する理論や計算問題が出題されることがありますが、問題文の細かい部分を理解し、どの方式が適用されているかを確認することが大切です。解説に従い、計算の基準をしっかりと把握して、正しい方法で問題を解くようにしましょう。
まとめ
基本情報技術者試験の過去問A科目問13では、スケジューリング方式の理解が試される問題でした。マルチタスクの概念を正確に理解し、ジョブの残り時間をどのように計算するかを確認することが重要です。5分を基準にした計算や、ジョブABCを同時に実行した場合の残り時間の取り扱いについてしっかりと把握することで、問題を解決できるようになります。
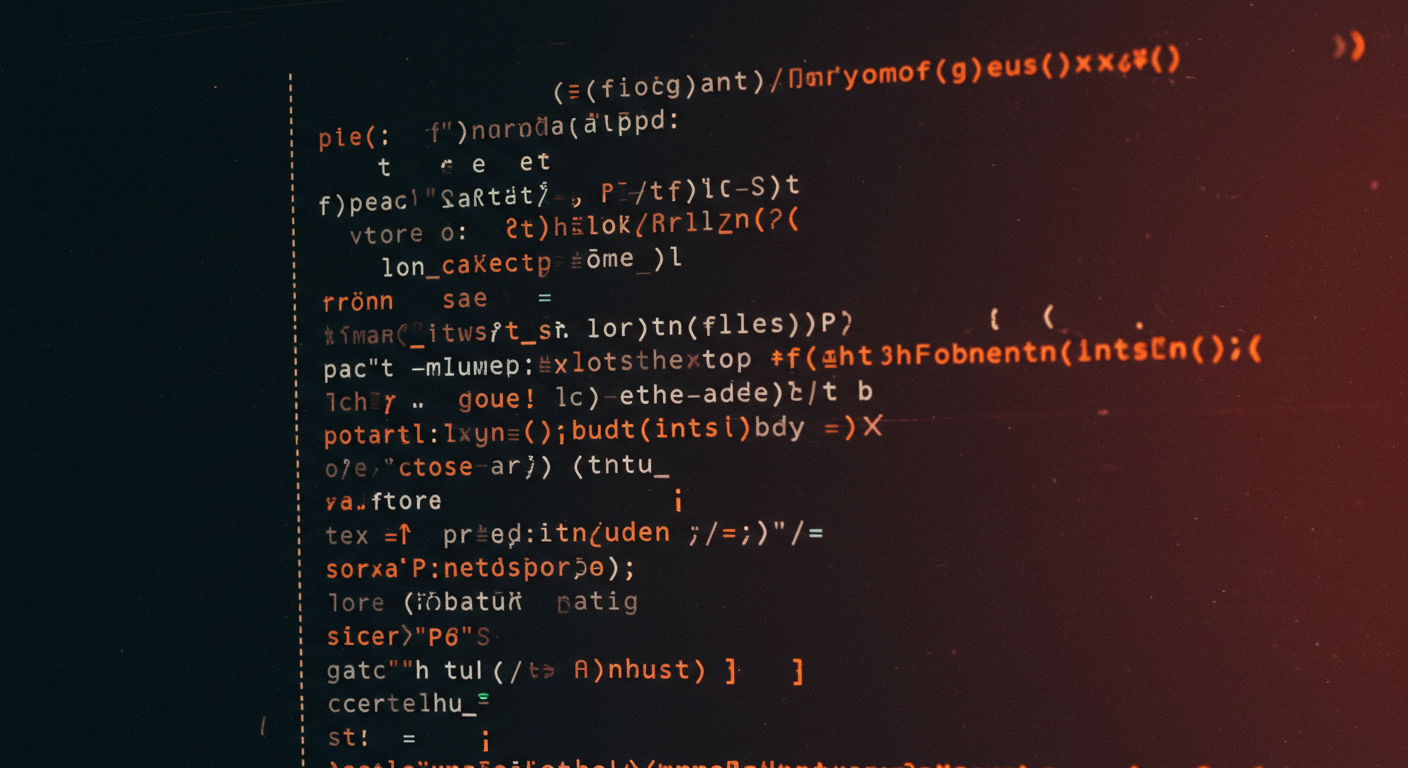


コメント