大学のデータベース課題で、与えられたテーブルを第3正規化し、対応するER図を作成する方法について解説します。課題内容に沿った具体的な手順を示すので、正しい正規化を理解し、問題を解決するための参考にしてください。
第3正規化とは?
第3正規化(3NF)は、データベース設計において、データの冗長性を減らし、効率的なデータ構造を作成するための手法です。3NFでは、すべての非キー属性が候補キーに対して直接的に依存している必要があります。つまり、推移的な依存関係を排除し、データが正しく分割されることを意味します。
課題のテーブル構造
課題で与えられたテーブルには、学生、教員、学科、科目に関する情報が含まれています。以下の条件に基づき、テーブルを第3正規化します。
- 学生、教員、学科、科目にはそれぞれ固有のIDがあり、それらが関連付けられています。
- 教員は1つの学科に所属し、学生は複数の科目を受講します。
- 各科目には1名の担当教員が割り当てられ、教員は複数の科目を担当することがあります。
第3正規化の手順
第3正規化を行う際には、以下のステップに従ってテーブルを分割します。
1. 学生、教員、学科、科目のテーブルを作成
まず、学生、教員、学科、科目をそれぞれ別のテーブルに分けます。これにより、各テーブルには一貫したデータが含まれ、冗長性が減少します。
2. 学生科目テーブルの作成
学生と科目は多対多の関係にあるため、学生科目テーブルを作成して、学生IDと科目IDを関連付けます。
3. 教員科目テーブルの作成
教員と科目も多対多の関係にあるため、教員科目テーブルを作成し、教員IDと科目IDを関連付けます。
ER図の作成
第3正規化されたテーブルに基づいてER図(エンティティ-リレーション図)を作成します。ER図では、各エンティティ(学生、教員、学科、科目)がどのように関連し、データがどのように接続されるかを示します。具体的には、学生、教員、科目、学科のテーブルを四角で示し、リレーションシップを線で接続します。
まとめ
第3正規化とER図の作成は、データベース設計の基本的なスキルです。課題に従って正規化を行うことで、冗長性を減らし、効率的なデータ構造を作成できます。この記事で紹介した手順を参考に、課題を解決しましょう。正規化の過程を理解し、ER図を作成することで、データベース設計の基礎をしっかり学べます。
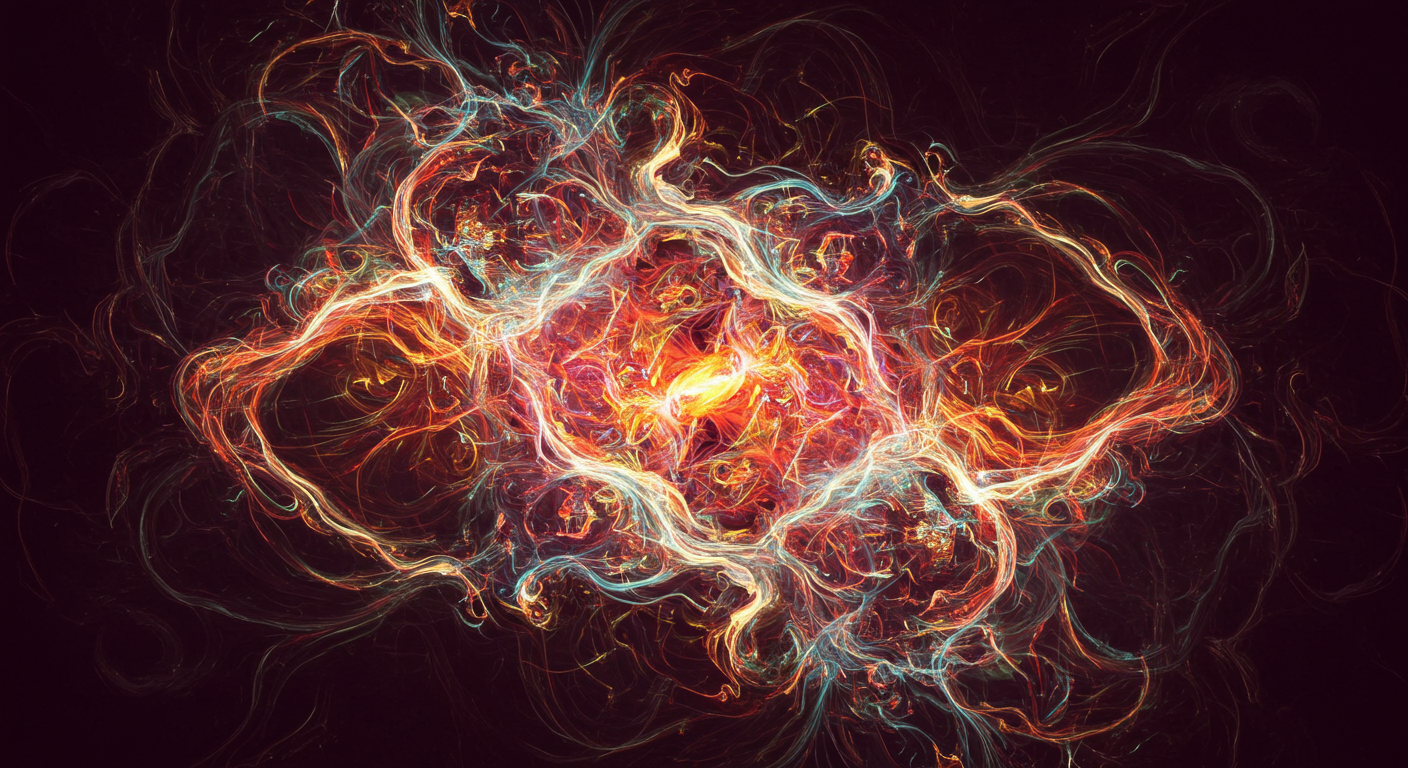


コメント