Pythonを使う際、外部ライブラリのインポート文は重要な役割を果たします。特に、scikit-learnのようなデータサイエンスに使われるライブラリでよく見られるインポート文ですが、最近のバージョンで書き方に変更があり、以前と異なる動作を見せることがあります。特に、`from sklearn.externals import joblib`と書くのが一般的でしたが、最近では`import joblib`のように変更され、少し違和感を感じる方も多いのではないでしょうか。この記事では、この変更について説明します。
1. `from sklearn.externals import joblib`と`import joblib`の違い
以前のscikit-learnでは、`joblib`を外部ライブラリとして`sklearn.externals`からインポートする方法が主流でした。これによって、`joblib`を直接インポートすることなく、scikit-learnの一部として使用することができました。しかし、最近のバージョンのscikit-learnでは、このインポート方法が廃止され、`joblib`を直接インポートする形に変更されています。
具体的には、`import joblib`のように直接インポートすることが推奨されており、これによりインポートがシンプルになり、外部ライブラリを使う際の依存関係も簡単に管理できるようになりました。
2. なぜ`import joblib`に変更されたのか?
この変更の主な理由は、`joblib`がscikit-learnの外部ライブラリとして依存関係が減少し、独立して更新や管理を行えるようになったことです。以前は`sklearn.externals`に含まれていた`joblib`ですが、より効率的なパッケージ管理とアップデートのために、`joblib`が独立した外部ライブラリとして提供されるようになりました。
これにより、`joblib`のバージョン更新が他のscikit-learnのアップデートに依存せず、独立して行えるようになり、パフォーマンスや機能向上が促進されています。
3. 実際のコード例と変更点
例えば、以前のコードは以下のように書かれていました。
from sklearn.externals import joblibこれが最近のバージョンでは、以下のように変更されています。
import joblibこの変更により、コードが簡潔になり、依存関係の管理がより直感的になっています。
4. まとめ
`from sklearn.externals import joblib`から`import joblib`への変更は、Pythonとその外部ライブラリの管理が進化する過程で行われた重要なアップデートです。この変更により、コードはよりシンプルになり、外部ライブラリの依存関係が管理しやすくなりました。もし、`joblib`を使っている場合、今後は`import joblib`を使用することを覚えておきましょう。
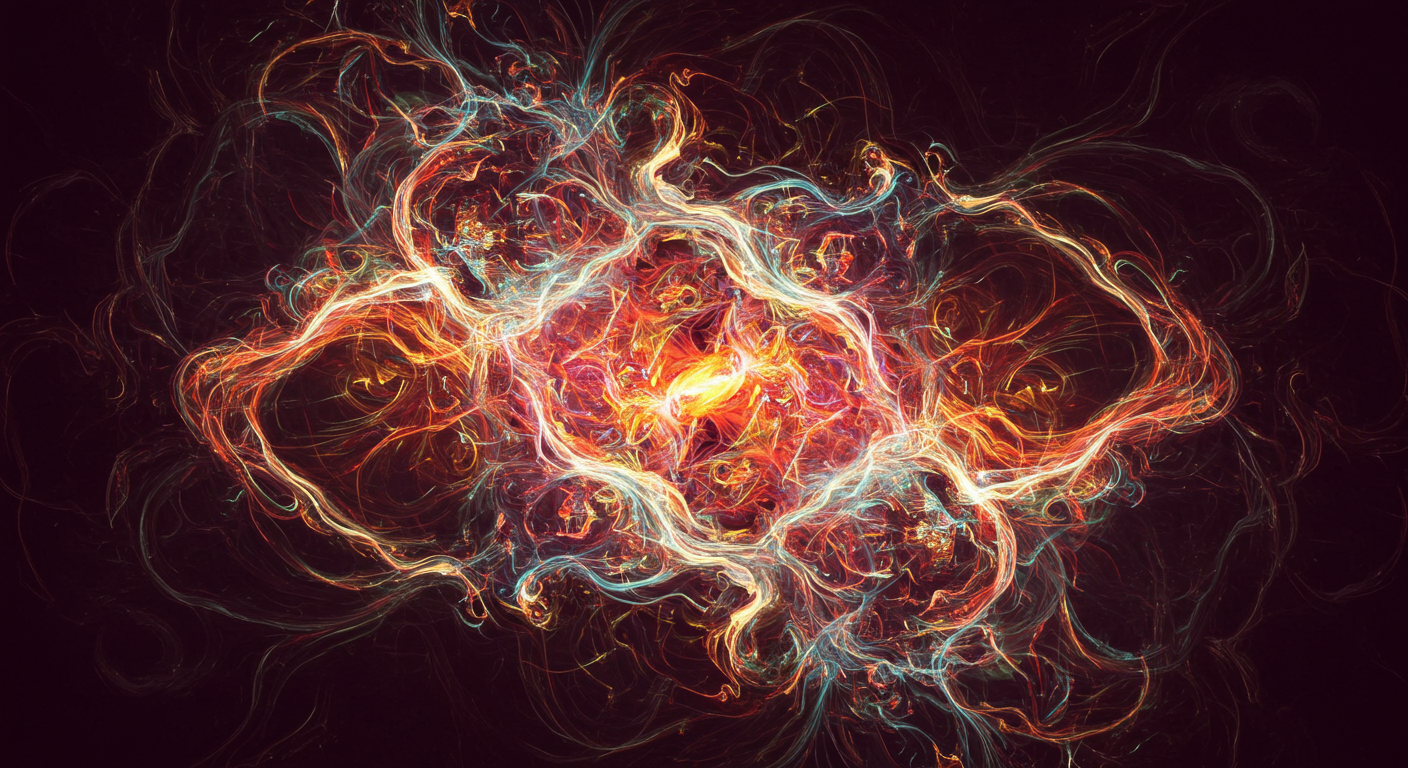


コメント