後置記法(ポストフィックス記法)で表された式をどのように評価するかを解説します。今回は、2つの後置記法の問題についてその解答方法を説明します。
後置記法の基本
後置記法では、演算子がオペランド(数値)より後に書かれます。例えば、通常の算術式では「A + B」のように演算子がオペランドの間にありますが、後置記法では「A B +」のように記述されます。
後置記法の評価はスタックを使って行います。スタックのトップに数値を積んでいき、演算子に出会ったときにスタックから数値を取り出して計算し、その結果を再びスタックに積みます。
問題1: YAB + C – DE ÷ × =
この式を評価するためには、順番に各要素を評価していきます。式をスタックで解く手順は以下の通りです。
- Yをスタックに積む
- Aをスタックに積む
- Bをスタックに積む
- +演算子で、AとBを加算し、その結果をスタックに積む
- Cをスタックに積む
- -演算子で、スタックからCと前の計算結果を引き算し、その結果をスタックに積む
- Dをスタックに積む
- Eをスタックに積む
- ÷演算子で、スタックからDとEを割り算し、その結果をスタックに積む
- ×演算子で、スタックから結果を掛け算し、最終結果を得る
この手順で計算を進めることで、最終的な解答を得ることができます。
問題2: YAB + CD – E ÷ × =
問題2も同様にスタックを使用して評価できます。手順は次の通りです。
- Yをスタックに積む
- Aをスタックに積む
- Bをスタックに積む
- +演算子で、AとBを加算し、その結果をスタックに積む
- Cをスタックに積む
- Dをスタックに積む
- -演算子で、スタックからCとDを引き算し、その結果をスタックに積む
- Eをスタックに積む
- ÷演算子で、スタックからEを割り算し、その結果をスタックに積む
- ×演算子で、スタックから結果を掛け算し、最終結果を得る
後置記法では、演算子が数値の後に来るため、このように順番に処理していきます。
まとめ
後置記法の評価はスタックを使って順番に処理していく方法です。今回紹介した2つの問題では、順を追って演算を行うことで解答を導き出すことができました。スタックを使うことで、演算の順序を簡単に管理することができます。後置記法の理解を深めるためには、実際に手を動かして演算してみることが重要です。
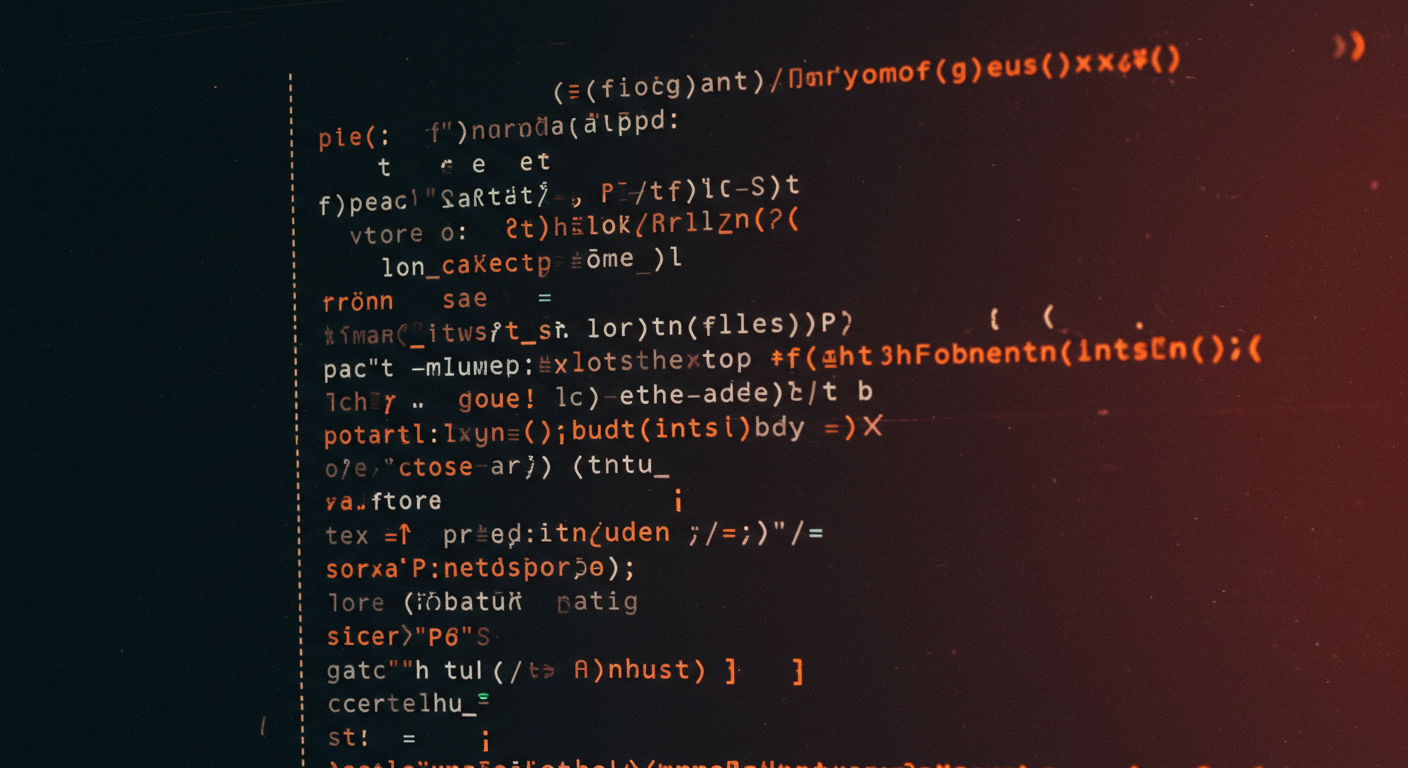


コメント