データベース設計において、概念データモデル、論理データモデル、物理データモデルはそれぞれ異なる目的を持ちます。これらのモデルの理解を深めることで、より効率的で適切なデータベース設計を行うことが可能です。この記事では、これらのモデルの正しい定義とそれぞれの違いについて解説します。
概念データモデルとは?
概念データモデルは、業務上の情報の構造やその関係性を抽象的に整理したものです。このモデルでは、データがどのように関連し合っているかを視覚的に示しますが、実際のデータの格納方法や構造に関する詳細は含まれていません。
例えば、顧客情報と注文情報がどのように関連しているか、顧客と注文の関係を示す「顧客ID」や「注文ID」などのキーがどう結びついているかを描きます。このモデルは、業務のプロセスを理解するための出発点となります。
論理データモデルとは?
論理データモデルは、概念データモデルを基に、データを正規化などを通じて繰り返しや冗長性を排除し、効率的なデータの格納方法を設計する段階です。この段階では、テーブル構造やリレーションなど、データベースの設計が具体的に定義されます。
正規化を用いることで、データの重複を防ぎ、データの整合性を保ちます。論理データモデルでは、例えば顧客情報と注文情報を別々のテーブルに分け、関連する情報を「外部キー」を使って結びつける方法が取られます。
物理データモデルとは?
物理データモデルは、論理データモデルを元に、使用するRDBMS(リレーショナルデータベース管理システム)の特性を考慮して、処理速度や運用性向上のために最適化されたデータ構造を設計します。
この段階では、インデックスの設定やデータ型、ストレージの最適化など、実際のデータベースのパフォーマンスを向上させるための具体的な設計が行われます。例えば、よく検索されるカラムにインデックスを設定することで、検索処理を高速化することができます。
概念データモデル、論理データモデル、物理データモデルの違い
これらのデータモデルは、データベース設計の異なる段階を表しています。
- 概念データモデル:業務の情報構造とその関係を抽象的に示す。
- 論理データモデル:正規化を行い、データを効率的に管理するためのテーブル構造を定義。
- 物理データモデル:RDBMSの特性に合わせて、パフォーマンスや運用性を最適化。
これらは、順を追ってデータベース設計を進める中で、各段階において重要な役割を果たします。概念データモデルが業務理解の基盤となり、論理データモデルがデータの整合性を確保し、物理データモデルが実際の運用での効率を向上させます。
まとめ
概念データモデル、論理データモデル、物理データモデルは、それぞれ異なる目的で使用されるデータベース設計の段階です。これらを適切に理解し、段階ごとに適切な設計を行うことが、効率的で運用に適したデータベースを作るための重要なポイントです。正しい理解を持って、業務要件を満たすデータベースを設計しましょう。
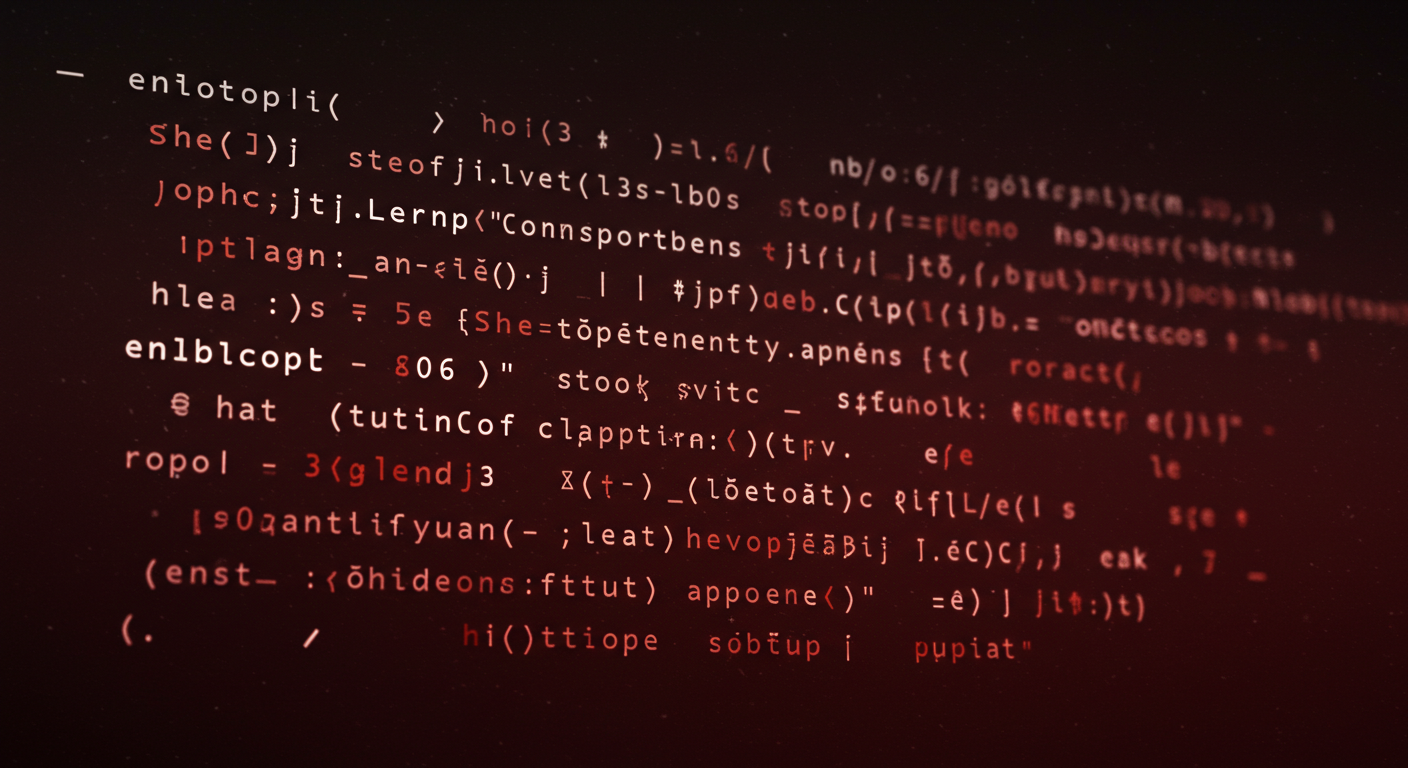


コメント