学校の授業で欠席や遅刻を記録するためにGoogleスプレッドシートを使用する場合、欠席の回数を自動で計算する方法を知りたい方も多いでしょう。特に、欠席1回を90分とし、欠席が複数回ある場合にその合計を自動的に算出できる仕組みは非常に便利です。この記事では、その方法をわかりやすく解説します。
欠席時間の自動計算をするための基本的な設定
まず最初に、Googleスプレッドシートを開いて、欠席や遅刻の記録用にカラム(列)を作成します。例えば、以下のようにカラムを設定します。
- 科目名
- 欠席回数
- 合計欠席時間
次に、欠席回数の列に「1」や「2」などの欠席回数を入力します。例えば、1回目の欠席なら「1」、2回目の欠席なら「2」と入力します。
自動計算を行うための数式を入力
次に、合計欠席時間を自動計算する数式を入力します。例えば、欠席回数が入力されたセル(例えばB2)に対して、欠席1回が90分で計算されるように次の数式を使用します。
=B2*90
この数式を使うことで、欠席回数が入力されたセルを基に、合計欠席時間を自動で算出することができます。B2セルに「1」と入力すれば、「90分」と計算され、B2セルに「2」と入力すれば、「180分」と計算されます。
複数科目の欠席時間をまとめる方法
もし、科目ごとに欠席時間をまとめる必要がある場合、各科目の欠席回数を記録する列を作成し、合計欠席時間をその都度計算します。例えば、以下のように科目ごとの欠席回数を入力する列を作成し、合計を計算する列に数式を入力します。
- 科目1欠席回数
- 科目2欠席回数
- …
- 総合計欠席時間
それぞれの欠席回数を入力した後、総合計欠席時間を計算するための数式を使います。
=C2*90+D2*90+E2*90
このようにすることで、複数科目の欠席時間を集計することができます。
まとめ
Googleスプレッドシートを使って欠席や遅刻の時間を自動的に計算するためには、欠席回数に応じて数式を使用することが重要です。これにより、手動で計算する手間を省き、効率的に時間を管理することができます。科目ごとに欠席時間をまとめることも可能なので、必要に応じて数式を調整し、用途に合わせてカスタマイズしましょう。
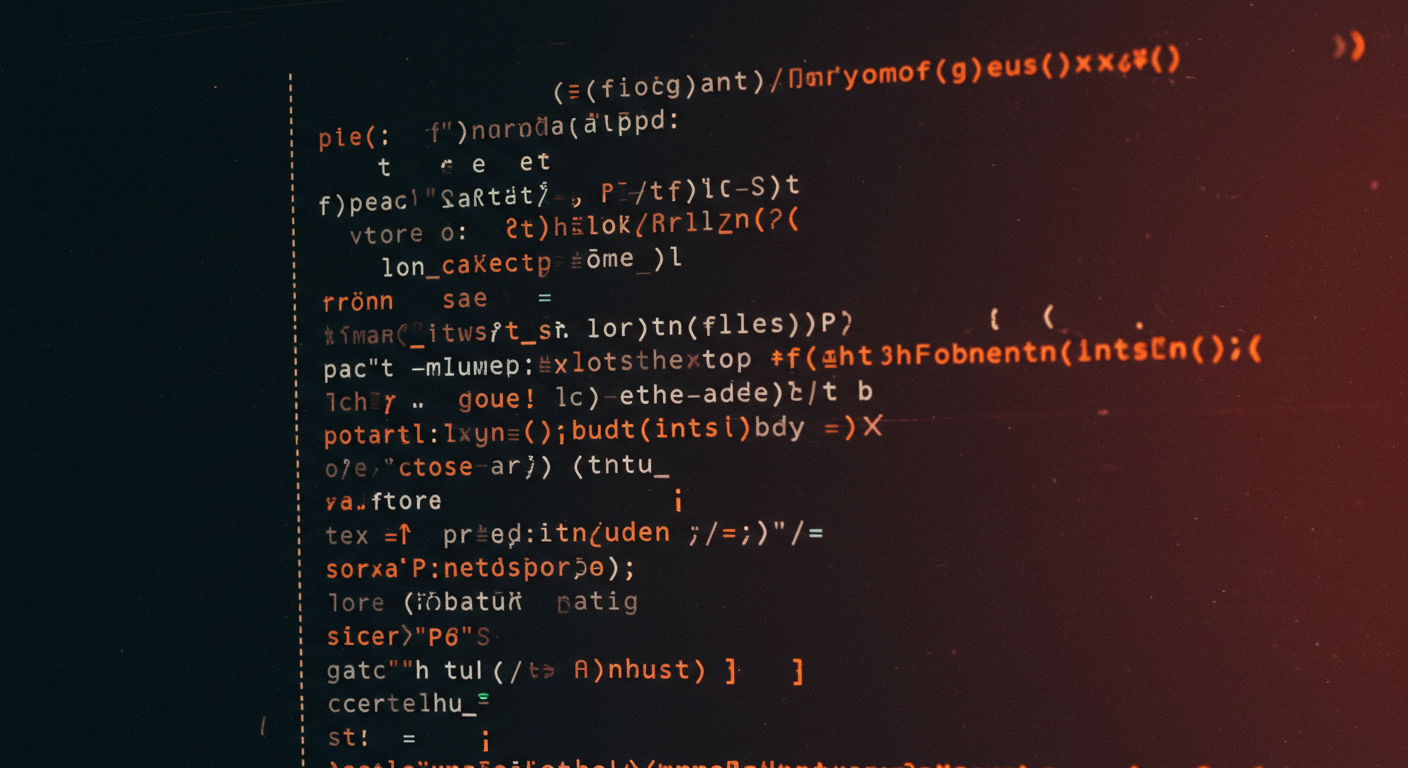


コメント