Pythonを学び始めたばかりの方にとって、文字列の使い方やprint関数の使い方は最初に覚えるべき基本の一部です。ここでは、文字列を囲む引用符(”)や、print関数の使い方に関する疑問を解決します。
1. 文字列を囲む””(ダブルクォーテーション)の使い方
Pythonでは、文字列を表現する際にダブルクォーテーション(””)やシングルクォーテーション(”)を使います。例えば、”りんご”を文字列として扱う場合、”りんご”というようにダブルクォーテーションで囲みます。文字列を囲むために”が必要ですが、値そのものには”は含まれません。シングルクォーテーションでも同様に、’りんご’として表現できます。
2. 数字には”は必要ない
数字(例えば、1)は文字列ではなく、数値として扱われるため、”(クォーテーション)で囲む必要はありません。したがって、answer=1という記述では、1はそのまま数値として処理されます。
3. print関数と()(丸括弧)の使い方
Pythonのprint()関数は、指定した内容を画面に表示するための命令です。print関数を使う際、print(apple)のように、関数名と引数を囲むために丸括弧(())が必要です。ここでappleは変数であり、文字列の場合はその中に”を使って囲んだ内容が入っているだけです。
4. どのような場合に”や()が必要か
文字列は”や”で囲みますが、数値や計算式には”や”は使いません。print関数の引数として、表示したい内容を丸括弧内に書くことが求められます。例えばprint(apple)のように書くことで、変数appleの内容が画面に表示されます。
5. まとめ
Pythonでは文字列を囲むために”(ダブルクォーテーション)や”(シングルクォーテーション)が必要です。数値を表示する際には囲む必要はなく、print関数を使うことで、変数の内容や文字列を表示することができます。最初はシンプルに、どのように文字列や数値を扱うかを学びながら進めていきましょう。
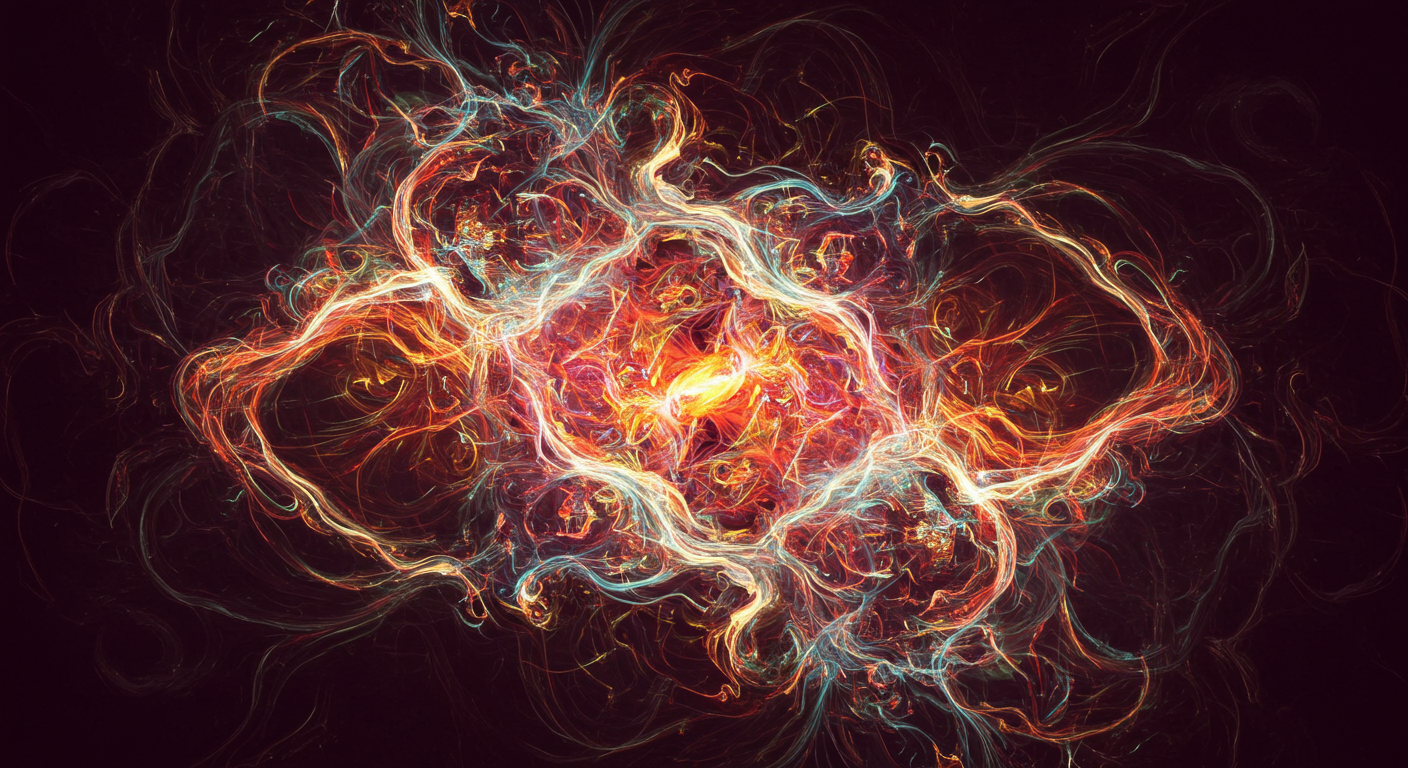


コメント